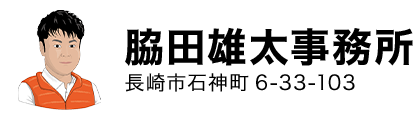〜 脇田雄太コラム 第26回 〜 「長期安定的な収益を実現しよう!」
こんにちは!
ボロ物件投資家の脇田雄太です。
みなさんもご存知かと思いますが、世の中の景気は、時代につれて大きな波があります。
例えば、私がまだ生まれていなかった昭和中期の頃は、戦後の復興から高度成長期にかけて大幅なインフレがありました。
さらに、昭和末期から平成にかけての「バブル景気」とその崩壊、2008年のリーマンショックを経て、長かったデフレから現在はインフレに向かっています。
不動産投資も、そのような景気や不景気の大きな波に、翻弄されながら現在に至っているといえます。
ただし、短期的な転売を除く不動産投資は、株や先物取引などと違い「長期的な視点で考えること」が必要であり、数年レベルで投資の成否を評価出来るものではありません。
どんな物件であれ、10年後や20年後の投資を見越した上で、「長期安定的に儲かる物件を保有する」ことが、何より重要というわけです。
今回は、そんなテーマで書いてみたいと思います。
===========
大都市部のインフレ
===========
近年、東京や大阪、名古屋、福岡や札幌などの大都市部では、「不動産価格の高騰」
が、大きな話題となりました。
冒頭でも触れたように、これまで長かったデフレ期を脱して不動産価格がインフレに転じるというのは、この業界にとっても明るいニュースであることは間違いありません。
その一方で、かつてはキャッシュフローを得られていた収益物件が、物件高騰の煽りを受けて、「利回りがジリジリと低下する」事態も起こっています。
物件価格の上昇に賃料が追い付かないことから、キャッシュフローがプラスどころか、持ち出しになっているケースもあるんですね。
さすがに首都圏でも、2024年後半から相場の伸びは一段落しているようですが、物件価格の大きな下落がない限り、今後も難しい投資が続くことは間違いないといえるでしょう。
===========
分厚い利回りマージン
===========
一方、長崎などの地方都市では、中古物件の価格や供給が安定していることもあり、大都市レベルの利回り低下は起きていません。
賃料相場の上昇はあまり期待出来ませんが、大都市部に比べれば安定的な運営が出来るというわけです。
そもそも、地方ボロ物件の実質利回りは控えめにみても10数%、高ければ30%以上が期待出来るため、将来的なコスト高に見舞われたとしても、「分厚い利回りのマージン」によって、その影響を吸収出来る強みがあります。
例えば、大都市部の物件で表面利回りが6%から3%になったら、キャッシュフローがマイナスに転じる一大事です。
しかし、実質利回り20%のボロ物件が10%に落ちたとしても、満室を維持することが出来れば、「長期的な維持運営は十分に可能」なんですね。
そういう意味で、インフレ局面における地方のボロ物件投資は、「時代の波に左右されない安定した投資」だと言えるでしょう。
===========
コストの上昇は相殺出来る?
===========
とはいえ、利回り的に優秀なボロ物件投資も、ここ数年の間で風向きが少し変わって来ました。
それは何か?というと、「リフォームコストの上昇」。
少子化や職人さんの高齢化に伴い、建設業界は近深刻な人手不足に見舞われており、リフォーム工事に伴う人件費もじりじりと上昇しています。
さらにコロナ禍以降は、建物の部材や設備などのインフレも起きているため、私がボロ物件投資を始めた2000年代後半のデフレ期に比べると、リフォームコストが上昇していることは否めません。
しかしその一方で、地方ではボロ物件の供給も増えているため、「より良質な物件をより安く買える」という状況が、コロナ禍以前に比べて顕著になっています。
つまり、リフォームコストの上昇は、物件価格で相殺出来るということです。
例えば、修繕やリフォームのトータルコストが50万円上がったとしても、
・物件を50万円安く買う
・より程度の良い物件を買う
ことでプラマイゼロなら、同じ実質利回りがキープ出来ますよね?
===========
時代に左右されない投資
===========
さて、今回のコラムはいかがだったでしょうか?
冒頭でも述べたように、かつてのバブル景気やリーマンショックなど、不動産業界も時代の波に大きく翻弄された歴史があります。
不動産投資もここ20年ほどで、フルローンを重ねて物件規模を急拡大するスキームが流行ったかと思えば、地方のボロ物件投資のプレイヤーが急速に増加するなど、さまざまな変化がありました。
不動産投資は「時間を味方に付ける投資」であり、どの投資法が正解だったかは後になって分かるものです。
その上で、何よりも大切なのは、「長期安定的な収益を実現する」ことだと、私は確信しています。
打ち上げ花火みたいに派手にパッと散るのではなく、火鉢にくべた炭火のように
じわじわと長く燃え続ける、そんな投資を目指したいですね。
今回はこのへんで。
脇田雄太でした。